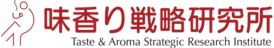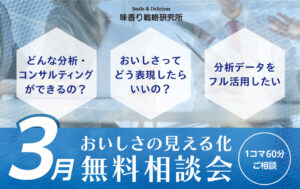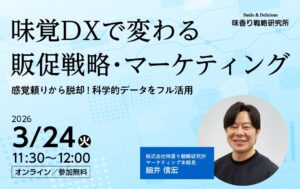「食」を科学する株式会社味香り戦略研究所(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小柳道啓、以下「味香り戦略研究所」)は、12万件超の味覚データベースを保有し、味覚センサで測定したデータ等を活用して、おいしさの課題に対するソリューションを提供しています。味覚センサは通常、常温での測定が一般的ですが、飲食料品の味わいは温度によって大きく変化します。しかし、現状では、味覚センサでの測定やそのデータには様々な課題があります。そこで、味香り戦略研究所は、常温での味覚センサ測定値から各温度帯の味わいを推定する手法を開発しました。
味香り戦略研究所は、温度別の味わいを数値化し、従来の味データに加わる新たなデータとして、販売促進や商品PRへの活用をサポートし、さらに、独自の技術とかけ合わせて消費者の嗜好に合った飲食体験を提案します。

サマリー
●温度変化が味わいに与える影響を、日本酒・コーヒー・めんつゆの3種類を用いて味覚センサと官能評価を併用して解析しました。
●各食品カテゴリーごとに、その解析結果を用いて、味わいの推定式を構築できる可能性が示唆されました。
●味香り戦略研究所が有する嗜好性データやフードペアリング技術とかけ合わせることで、個人の好みの温度の推定や、飲食料品の組み合わせで最適な温度を提示することができます。
温度が味わいに与える影響は、飲食体験を左右する重要な要因です。高温になると強くなる味わいや、反対に高温で弱くなる味わいもあるため1)、同一の飲食料品でも提供温度により味わいのバランスが変化します。そのため、コーヒーや蕎麦のように冷・温のどちらでも楽しめる飲食料品では、温度帯によって味の感じ方が異なります。
味覚センサは味わい(基本五味+渋みの先味と後味)を数値化できる装置ですが、温度変化に伴う味わいの変化を調べるには、その都度、循環式恒温装置で水温を調節した循環水を用いて、測定対象を各温度帯に調整する必要があります。また、温度変化によりセンサ劣化が進むこともあり、通常よりもコストのかかる測定方法になります。加えて、同一温度内のサンプル比較(例:10℃のサンプルAと10℃のサンプルB)は可能でも、異なる温度間の比較(例:10℃のサンプルAと20℃のサンプルA)をすることはできませんでした。
そこで、味香り戦略研究所では、このたび、味覚センサの常温測定値から各温度帯の味を推定する予測式を開発し、常温測定のみで異なる温度帯の味わいを数値化できる方法を検討しました。
試験設計
本試験では、味覚センサの常温測定で、各温度帯の味わいを推定できるようにすることを目的としました。試験サンプルは冷・温の両方の喫食シーンが想定できる日本酒・コーヒー・めんつゆの3種類としました。
〈測定方法〉
〇味覚センサ(株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー製 TS-5000Z)
サンプル(付表1)を50℃、3℃に調製し、常温(約20℃)の環境下で温度保持の処理を実施せず測定しました。
〇官能評価
調整温度5℃・20℃・45℃の3条件でサンプルを提供し、各評価項目について「味の強さ」について評価しました。
考察
味覚センサデータと温度の関係性
うま味後味や苦味先味などでは、温度上昇によって飲料・調味料によって味を強める、弱めるといった両面性が確認できました。また、呈味化合物により温度による傾向は異なることが示唆されており2)、塩味は呈味物質の濃度によって異なることも報告されており3)、既存の結果でも一律ではないことが示されています。
また、飲料・調味料ごとでは、日本酒の塩味先味とコーヒーの苦味先味を除く全ての項目で有意な相関が確認されました(p<0.05)(図2)。これら2項目では、センサ値は大多数の人に味の違いを認識されないとされる変動幅1.0未満であることから、温度変化しても味わいは変化しないと考えられました。そのため、温度帯ごとの味わい推定式は飲料・調味料別に作成すべきと考えられました。

味覚センサでサンプルごとに常温で測定した値と算出した回帰式を用いて、5℃、20℃、45℃以外の温度帯でも味わいを推定することができるようになりました。
今回開発した推定式による温度別の味データの推定結果については、官能評価による検証を行い、味の変化がおおむね同様の傾向を示したことを確認しています。
本試験の詳しい内容は、2025年6月26日開催のオンラインセミナーにて解説します。
開催概要
| タイトル | 温度で変わる“おいしさ”を可視化 温度×味データ活用術 |
| 日時 | 2025年6月26日(木)11:00~11:35 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社味香り戦略研究所 |
| お申し込み・詳細 | https://mikaku.jp/seminar/2025/11013/ |
温度帯別味覚データの活用方法
温度によって変化する味わいを数値化することで、従来の味データと同様、販売促進や消費者への情報発信、また品質管理に活用でき、科学的な根拠をもった訴求が可能になります。
また、味香り戦略研究所が保有する嗜好性データや独自の嗜好性診断技術、フードペアリングの技術とかけ合わせることで、パーソナライズされた味わいを作り出すなど、より深い飲食体験を提案します。
消費者への提供価値として―適温で味わう飲食体験
販促活動においては、温度による味わい変化を体験価値として演出することが可能です。すでに親しまれている商品であっても、温度によって違う味わいを楽しむことを訴求することで新たな魅力を伝え、ブランドへの愛着と購買意欲を喚起できると考えます。
より直接的には、販促資材に味データを図示することも考えられますが、キャッチコピー等、おいしさを伝えるための文章表現においてもエビデンスに基づくプロモーションが可能となります。
また、変化する味わいを把握できることで、飲食店では提供温度を最適化し、苦味や酸味を抑えつつうま味を強調するというような味わいの設計が可能になり、「常に一定の味わいを提供する」という品質の安定を実現します。製造現場であれば、官能評価における検査時の温度変動による誤差を排除し、ロット間の品質のばらつきを低減することが可能になると考えられます。
温度による味わい変化を利用した味の組み合わせ提案―パーソナライズとフードペアリング
個人の味の好みである嗜好性は、コレスキというツールで判別でき4)、日本人の好みは22パターンに分類されます。このデータと、味覚センサでの温度変化による味わいの推定をかけ合わせることで、個人の好みの味わいになるような飲食料品の温度にすることも可能となります。
本試験で用いためんつゆのデータを例に、冷たい時をざるそば、温かい時をかけそばとすると、苦味が好きな「おやじ舌-C」タイプにはつゆの素のざるそばが、苦味が苦手な「こども舌-C」タイプには創味のつゆのかけそばが嗜好に合う味わいになっていました【図3】。

また、フードペアリング技術では5)、味覚センサの味データを用いて飲食料品同士の相性の良い組み合わせを解析できます。本試験結果をかけ合わせると、相性が良くなる温度を明らかにすることも可能になります【図4】。本試験で用いた日本酒では、白鶴サケパックまるの冷酒が刺身と合っており、のものもの熱燗がおでんと合っていました。

今回実施した、日本酒、コーヒー、めんつゆに関しては、味覚センサで常温測定を実施することで、算出した回帰式から各温度帯での味わいを推定できるようになりました。今後は、より多様なサンプルを追加して予測モデルの精度を検証します。
また、本手法は日本酒、コーヒー、めんつゆ以外の飲食料品にも適用可能であり、温度依存による味わい変化を定量的に評価できます。今後は、対象飲食料品の種類を増やすとともに、日本酒と焼酎など類似製品間で同一の予測モデルが適用できるかどうかといったモデルのカテゴライズも検討していきます。
引用
1)Hahn H(1936)Über die Ursache der Geschmacks-Empfindung, Klin. Wschr., 15, 933-935.
Mowery L (2023) The do’s and don’ts of chilling wine, Wine Enthusiast. https://www.wineenthusiast.com/basics/chill-wine/
2)髙橋貴洋(2020)「うまい!」の科学データでわかるおいしさの真実,イースト・プレス
3)Talavera K, Ninomiya Y, Winkel C, Voets T, and Nilius B (2007) Influence of temperature on taste perception, Cell. Mol. Life Sci., 64, 377-381.
4)小柳道啓、早坂浩史、藤丸順子、近藤環、高橋貴洋(2024)嗜好商品情報提示装置及び嗜好飲料・食品情報提示装置,特許第7448274号
5)小柳道啓、早坂浩史、藤丸順子、近藤環、高橋貴洋、峰吉祐介(2023)飲料と食品、料理と調味料、調味料、食品構成材料それぞれの相性情報提示装置及び飲料と食品の相性診断方法,特許第7398855号
味香り戦略研究所について
「食」を科学する味香り戦略研究所は、味・香り・食感等の「おいしさ」の見える化をコア技術に持つソリューション提供企業です。12万件超の味覚データベースを構築し、それを基に独自の嗜好性診断アルゴリズム(特許第7448274号)、フードペアリングロジック(特許第7398855号)を開発。食品開発・マーケティング支援など、食にまつわるさまざまな課題に対応するフードデジタルソリューションを提供し、パーソナライズド提案技術の社会実装にも積極的に取り組んでいます。
【会社概要】
株式会社 味香り戦略研究所【https://mikaku.jp/】
本社所在地:東京都中央区新川1-17-24 NMF茅場町ビル8F
代表取締役社長:小柳 道啓
設立年:2004年9月
事業内容:フードデジタルソリューション事業
本件に関する問い合わせ先
味香り戦略研究所 コンサルティング事業部
TEL 03-5542-3850 / お問い合わせフォーム
付表1 試験サンプル
日本酒
| 白鶴酒造 | 白鶴 サケパック まる |
| 月桂冠 | つき |
| 宝酒造 | 松竹梅 天 |
| 黄桜 | 辛口一献 |
| 大関 | のものも |
コーヒー
| ネスレ日本 | ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 |
| 森永乳業 | マウントレーニア カフェラッテ |
| サントリーホールディングス | ボス とろけるカフェオレ |
| 名古屋製酪 | ホテルレストラン仕様コーヒー無糖 |
| 日本コカ・コーラ | ジョージア カフェラテ |
めんつゆ
| にんべん | つゆの素 |
| ミツカン | 追いがつおつゆ |
| キッコーマン | 濃いだし本つゆ |
| 創味食品 | 創味のつゆ |
| ヤマキ | めんつゆ |